

能美防災では、一人ひとりの挑戦や想いがキャリアのかたちをつくり、そこにはそれぞれの歩みが育んだ多彩なストーリーがあります。
ここでは、実際に働く社員の声を通じて、能美防災で広がるキャリアの可能性をご紹介。あなたの未来を重ねてみるヒントになれば幸いです。





-
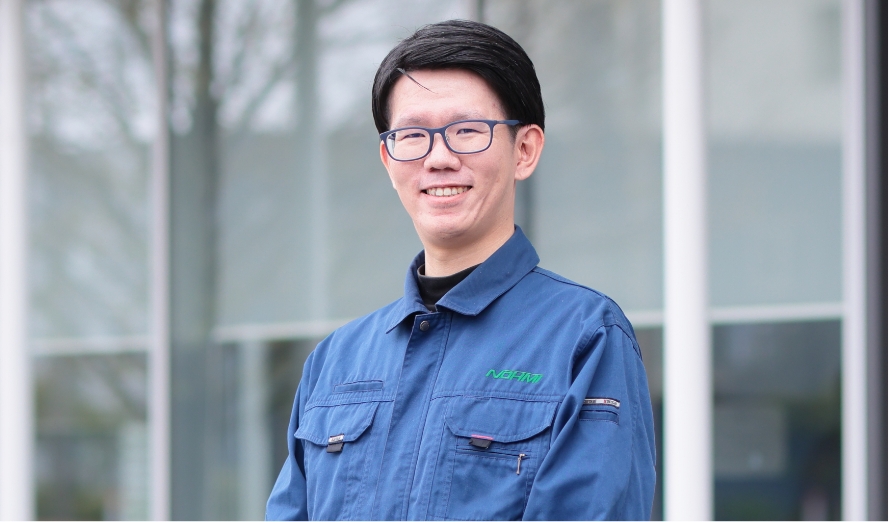
未知への挑戦を恐れず、
技術の力で未来の安心を切り拓く。-
入社1年目研究開発部門(先進技術研究室)へ配属
-
入社2年目構造物のモニタリングシステムの研究チームに加わり新規研究に挑戦
-
入社6年目煙検知システムで課題解決と実証実験の主担当に
-
入社10年目画像処理研究を軸に様々な業務を完遂し、プロジェクトリーダーへ
N.I研究開発センター先進技術研究室工学部 知能情報工学科卒2013年度 入社研究開発を主体とする部署で、多様なテーマに主体的に取り組んできました。構造物モニタリングのような新領域への挑戦や、画像処理技術の社会実装などを通して、専門性だけでなく課題解決力やマネジメント力も身につけてきました。近年は他部署や現場との連携も増え、技術を現場視点で捉える視野が広がったと実感しています。
今後の目標長年携わってきた画像処理煙検知システムの普及を進めることが、当面の目標です。現行システムの取り扱いには高い専門性や深い理解が求められ、導入の際のハードルとなっています。そうしたハードルを少しでも下げるため、他部署と連携しながらユーザーフレンドリーなシステムを目指し、社会の安心・安全に技術で貢献していきたいと考えています。
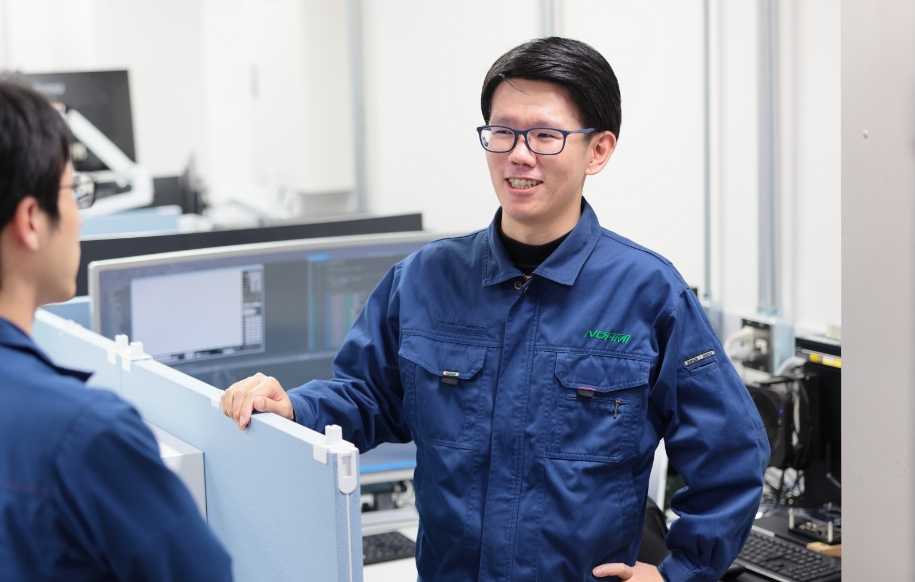
-
-
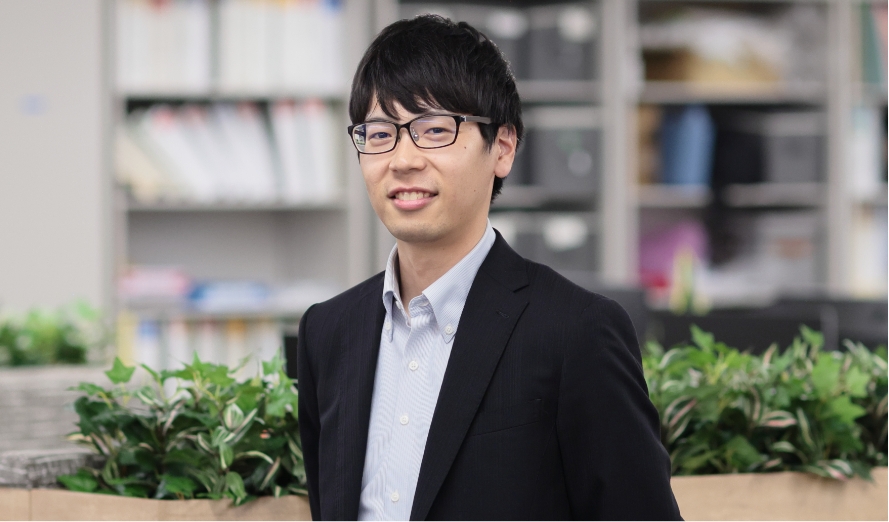
研究開発の知見を活かし、
現場で求められる技術を届ける。-
入社1年目研究開発センター第2感知システム研究室へ配属
-
入社2年目研究開発部門で新製品の電気設計を担当
-
入社5年目〜現在応用技術課で開発・営業・技術支援を担当
T.Y技術本部第1技術部第1応用技術課理工学研究科 電気工学専攻2017年度 入社入社以来4年間は研究開発部門に所属し、新製品の開発に携わってきました。電気設計や品質試験などの業務を通じて、製品の根幹をつくる重要性と責任感を実感しました。その後、応用技術課へ異動し、工場やプラントなどの現場調査や顧客対応を行う中で、現実のニーズや課題を肌で感じるようになりました。研究職で培った知識や技術が、現場で求められる製品提案や技術支援にも活かせることにやりがいを感じています。現在では、開発支援や営業支援、技術資料作成まで幅広く関わるようになり、視野も業務範囲も着実に広がってきたと実感しています。
今後の目標自主設置製品の種類が多い中で、まだ把握しきれていない製品も多くあります。今後はそれぞれの特徴や用途を深く理解し、あらゆるシーンで最適な製品提案ができる技術者を目指します。また、お客様のニーズに合わない場合でも、声を製品開発に活かす橋渡し役となり、新たな製品の企画にも挑戦していきたいです。

-
-

人とのつながりを力に変え、
信頼で築く提案力を磨き続ける。-
入社1年目火報設備本部 第1システム施工部へ配属
-
入社5年目営業部門に異動し、提案営業に従事
K.K営業本部 営業4部経済学部 経営学科卒2016年度 入社入社後は施工管理部門で経験を積み、現場や納品までの一連の流れを理解することができました。その後、営業部門へ異動し、提案や価格交渉といったフロント対応を通じて、お客様との関係構築や数字への意識が一層高まりました。業務を通して実感しているのは、良いものづくりに不可欠なのは「人とのつながり」です。現場を動かすにも、提案を実現するにも、社内外の多くの関係者との協力が不可欠であり、その信頼関係の大切さを常に感じながら仕事を進めてきました。
今後の目標今後も、社内外を問わず共に仕事をする人たちと信頼関係を築き、チームでより良い製品を納められるよう努力を続けていきたいです。また営業としては、より大きな利益を生み出せる存在へと成長していきたいと考えています。そのために知識の習得や情報収集にも積極的に取り組み、人脈を広げながら営業活動の質を高めていきます。将来的には営業領域にとどまらず、様々な分野の仕事にもチャレンジし、自身の可能性を広げていきたいと思っています。

-
-

働き方も、専門性も。
変化を味方に、自分らしく前へ。-
入社1年目第3システム施工部へ配属
-
入社5年目設計部門に異動。設備図面・積算を担当
-
入社8年目育休を経て、働き方を変えながらこれまでの業務に従事
-
入社11年目2度目の育休を経て、後輩育成にも携わる
M.Yエンジニアリング本部第2エンジニアリング部工学部 電気工学科卒2013年度 入社施工現場でキャリアをスタートし、その後は設計部門へ異動しました。現場経験があったことで、図面や設備の理解がしやすく、業務にもスムーズに馴染むことができました。ライフイベントを経て働き方が変わる中で改めて感じたのは、今の働き方を実現できているのは、上司や同僚の理解と支えがあってこそだということです。現在は、設計業務の専門性を深める一方で、後輩や営業にアドバイスをする機会も増え、チーム内での役割にも広がりを感じています。今後は、自分が支えてもらったように、後輩たちにとって頼れる存在になっていきたいと考えています。
今後の目標現在は倉庫や文化財など、専門分野を絞って設計を担当していますが、今後はこれまであまり経験のない設備設計にも挑戦したいと考えています。防災設備は一見変化の少ない分野に見えますが、環境規制や産業構造の変化など、時代の流れにあわせて常に進化しています。そうした新しいニーズに応える設計にも携わり、特に新商品が初めて導入される案件で、自分の描いた図面が形になる経験を積んでいきたいです。

-
-

現場で鍛えた施工力と人間力で、
選ばれる担当者を目指す。-
入社1年目消防設備士甲種4類取得後、横浜支社施工管理課へ駐在
-
入社3〜6年目駐在から復帰し、第1システム施工部へ配属
-
入社7〜11年目中大規模案件を牽引し、自身の施工スタイルを確立
-
入社12年目〜現在第1システム施工部の係長に
T.N火報設備本部第1システム施工部経済学部 経済学科卒2009年度 入社新入社員研修と資格取得を経て、現場の最前線からキャリアがスタートしました。経験を積むごとに現場規模も責任も大きくなり、大型案件では施工管理だけでなく、他業者との調整やチームマネジメントの重要性を実感しました。中堅期には自分のスタイルを確立し、現場の一体感を大切にしながら仕事の面白さを感じるように。現在は係長として部下やチームを支えながら、「能美防災の施工担当者に任せたい」と思ってもらえる仕事を目指し、現場力と組織力の両立を追求しています。
今後の目標建設業界は今、大きな転換期を迎えています。働き方改革や業界イメージの向上が求められる中で、私自身は、部下やこれから入社してくる仲間たちに「能美防災の施工担当者でよかった」と思ってもらえるような環境づくりをしたいと考えています。これまでの経験を活かしながらも、新しい視点や柔軟な考えを持って、今までにない施工スタイルを確立していきたい。そして、施工の現場から防災業界をリードする存在として、No.1のチームを目指していきます。

-
-

支えてもらった経験が、
今の自分を、そして次へつなぐ力になる。-
入社1年目CSサービス部 第2グループへ配属
-
入社2年目消防設備点検契約物件の担当を持つ
-
入社4年目初めて大規模物件を担当。また新入社員教育も担当する
-
入社6年目同部第6グループへ配属(異動)、さらに大型案件を担当
Y.NCS設備本部 CSサービス部第6グループ経営学部 経営学科卒2017年度 入社入社後は研修や現場同行を通じて消防設備の知識を身につけ、2年目からは担当物件を持ち、点検から更新提案まで幅広く携わってきました。経験を重ねる中で、大規模物件や改修工事など難易度の高い案件も任されるようになり、業務の質と量のバランスを取る難しさも実感しました。そんな中でも、周囲のサポートを受けながら業務を進めてきたことで、チームで働くことの大切さを深く学ぶことができました。今では自身のスキルにも自信を持てるようになり、業務に対する姿勢や視野も大きく広がったと感じています。
今後の目標これまでは「あなたは頼りになる」と言っていただけるように努力してきましたが、今後は「能美防災は頼りになる」とお客様に思っていただけるような仕事を目指しています。担当が誰であっても、会社全体として高い品質のサービスを提供できるような体制をつくることが、結果的に次の仕事にもつながると感じるようになりました。そのために、自分だけでなくチーム全体の力を高めることに注力し、組織としての信頼性を高められるような働き方を目指していきたいと考えています。

-
